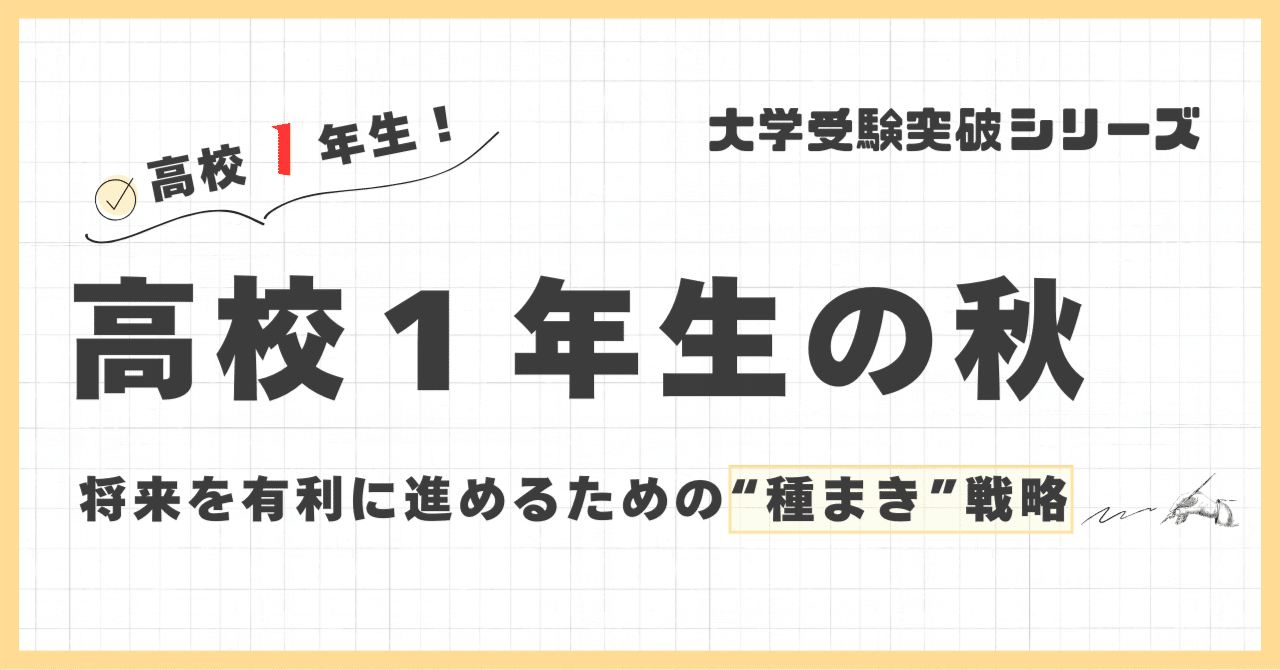ニュース&トピックス
教育情報・お知らせ
2025.11.15
【大学受験突破シリーズ】高校1年生の秋 将来を有利に進めるための「種まき」戦略[高1生 対象]
2025年11月2日 10:00
高校生活にも慣れ、部活動や新しい友人関係が落ち着いてくる秋。
高校1年生にとって、この季節は「受験の助走を始めるタイミング」と言っても過言ではありません。
大学受験は高3の1年間だけで完結するものではなく、3年間をどう積み重ねるかで結果が大きく変わります。
実際、難関大合格者の多くが「高1の秋」から学習のペースを整え始めています。
では、この時期に何を意識すれば将来の自分を有利にできるのでしょうか。
ここでは、「今すぐ取り組むべき3つの重要ポイント」を紹介します。

① 学習スタイルを確立し、基礎を徹底的に固める
高校の勉強は、中学の延長ではありません。範囲が広く、抽象度も高いため、
「わかったつもり」のまま進むと、気づいたときには取り返しがつかなくなってしまうこともあります。
だからこそ、この秋は“基礎固め”と“勉強スタイルの確立”に力を入れましょう。
まず大切なのは、「学習時間より学習頻度」。
1日3時間勉強が理想といわれますが、最初から長時間を目指す必要はありません。
大切なのは“毎日机に向かうリズム”をつくること。
1日30分でもいいので、勉強が生活の一部になるよう習慣化を意識してください。
そして、勉強の流れは「予習 → 授業 → 復習」が基本。
予習で“わからないところ”を明確にし、授業で理解を深め、復習で知識を定着させましょう。
特に苦手科目は、後回しにせず早いうちに“弱点ノート”を作り、繰り返し復習するのが効果的です。
「わからない」をそのままにしない姿勢が、受験の成功を左右します。
② 文理選択を“戦略的”に考える
高1の秋から冬にかけて、多くの高校で文理選択の話が出始めます。
この決断は、大学の出願科目や将来の進路に大きく関わるため、慎重に考える必要があります。
注意したいのは、「数学が苦手だから文系」「理科が嫌いだから文系」といった消極的な理由で決めてしまうこと。
苦手意識で進路を狭めるのはもったいないことです。
「自分はどんな分野に興味があるのか」「どんなことに時間を忘れて取り組めるのか」という視点で考えてみましょう。
2025年度の大学入試からは、共通テストの内容や出題範囲も拡充されます。
特に「情報」や「数学C」の一部が重要視されるため、今から少しずつ触れておくのがおすすめです。
「先取り学習」は、高1の時間的余裕がある今こそできる有効な戦略です。
③ 五感を使った“自己分析と大学研究”を始める
まだ先の話だと思いがちな「志望校選び」も、実はこの時期から始めるのが理想です。
大学や学部を“名前”で選ぶのではなく、「どんな学びができるのか」「どんな環境で成長したいのか」を
自分の感覚で確かめることが大切です。
その第一歩が自己分析。
「できること(CAN)」「やりたいこと(WILL)」「やるべきこと(MUST)」の3つを書き出してみましょう。
何を学びたいかが見えてくると、将来への意欲がぐっと高まります。
さらに、オープンキャンパス(OC)やオンラインイベントへの参加もおすすめです。
実際に大学の雰囲気を肌で感じることで、「この大学に行きたい!」というモチベーションが生まれます。
高2以降は模試や定期テストで忙しくなるため、今のうちに行動しておくのがポイントです。
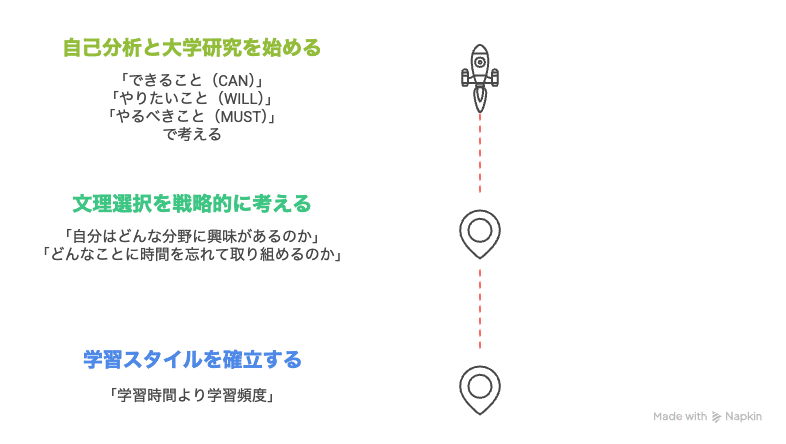
結び ― 今の“種まき”が、未来の“収穫”になる
受験は一朝一夕では成果が出ません。
でも、高1の秋に始めた小さな習慣や努力の積み重ねは、必ず2年後、3年後に大きな差となって現れます。
焦らず、しかし確実に。
この秋を、未来の自分を育てる“種まきの季節”にしてください。
きっと3年後、「あの秋に始めておいてよかった」と思える日が来ます。

noteでEFG(旧久保田学園グループ)の教育情報を発信しています。
⇨https://note.com/kubotag