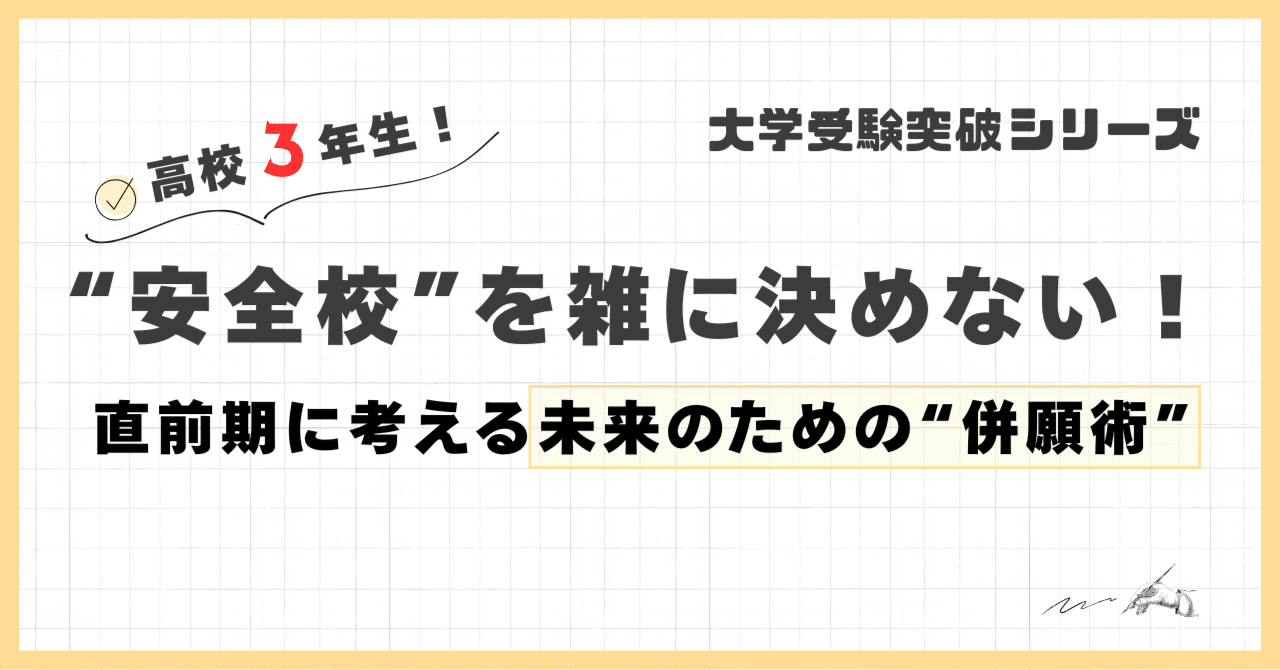ニュース&トピックス
教育情報・お知らせ
2025.11.15
【大学受験突破シリーズ】「安全校」を雑に決めない!─直前期に考える未来のための“併願術”[高3生対象]
2025年11月9日 10:00
共通テストまであとわずか。いよいよ受験が現実味を帯びるこの時期、多くの高3生が頭を悩ませるのが「併願校の最終決定」です。
「安全校を増やせば安心」「数を打てばどこかに受かる」──そんな声も聞こえてきますが、実は“数”よりも“質”が合否を左右することを知っていますか。ここでは、後悔のない併願戦略を立てるための3つの視点を紹介します。

1. 「行きたい理由」がある併願校を選ぶ
併願校選びで最も大切なのは、「受かったら通いたい」と思えるかどうか。
偏差値や立地条件ももちろん重要ですが、「ここで学びたい」と思える学問分野かどうかが、入学後の満足度を大きく左右します。
実際、進路指導の現場では、「第一志望に落ちても納得できる大学を選んだ生徒ほど、進学後に充実している」というデータもあります。
たとえば第一志望が法学部なら、併願も社会科学系でそろえるなど、“学びの軸”をずらさないことがポイントです。
専門家も「本命校を明確にすると、出題傾向が似た大学を効率的に選べる」と指摘します。
逆に志望の軸があいまいなままだと、無駄に出願校が増え、過去問演習が分散してしまいます。
「自分が本当に行きたい大学」を中心に、そこから枝を広げるように併願校を考える──これが第一の鉄則です。
2. 難易度のバランスを取る「ダイヤモンド型」戦略
安全校・実力相応校・チャレンジ校をバランスよく組み合わせる“菱形(ダイヤモンド)戦略”が、近年の王道です。
具体的には、チャレンジ校1〜2校、実力相応校2〜3校、安全校1〜2校で、合計4〜6校が理想的なライン。
実際、全国平均でも受験校数は3〜4校前後が主流です。
ここで大切なのは、「安全校」を本当に行きたいと思える大学に設定すること。
「滑り止めだからどこでもいい」と考えると、いざ合格しても進学をためらうことになります。
第一志望より偏差値で7〜10下、共通テスト得点率で10%下を一つの目安にしながら、心から納得できる“もう一つの道”を用意しておきましょう。
また、出願のしすぎにも注意。大学ごとに出題傾向や方式が違うため、やみくもに数を増やすと対策が散漫になります。
「下手な鉄砲も数撃ちゃ当たる」は、大学受験には通用しません。
3. 「タイパ」と「マネー」を制する現実的計画
受験は、時間もお金もシビアな戦いです。
だからこそ、スケジュール・費用・入試方式の3点を戦略的に設計することが成功の鍵になります。
まずスケジュール。理想は「右肩上がり」になるように組むこと。
安全校→相応校→チャレンジ校と難易度を上げていけば、緊張や本番慣れの不安を軽減できます。
ただし、連続受験は3日までが限界。体力的にも精神的にも、余裕のある間隔を確保するのが得策です。
次に「タイパ(Time Performance)」。
共通テスト利用入試の活用は、現代受験の必須戦略です。
一般入試よりも受験料が安く(平均で1〜2万円程度)、対策の重複が可能なため、最小の労力で最大の出願効果を得られます。
また、第1志望と同じ科目構成の大学を選ぶことで、併願校の勉強がそのまま本命校対策になるというメリットも。
そして最後に「マネー」。
合格後の入学金(平均20〜30万円)は原則返金されません。
合格発表と手続き締切の関係を必ず確認し、無駄な入学金を払わずに済むよう調整しましょう。
入学金延納制度やネット出願割引など、細かい情報も見逃せません。
おわりに
併願戦略とは、単なる「保険」ではなく、自分の未来をデザインするためのリスクヘッジです。
「行きたい大学」と「行ける大学」、そして「納得できる大学」。
その3つのバランスを自分なりに整理し、最終的に「後悔のない選択」をすることこそが、真の戦略的受験といえます。
今こそ、過去問の束を前に「どんな春を迎えたいか」を描いてみましょう。
そのイメージが、併願校選びの最良の羅針盤となるはずです。

noteでEFG(旧久保田学園グループ)の教育情報を発信しています。
⇨https://note.com/kubotag