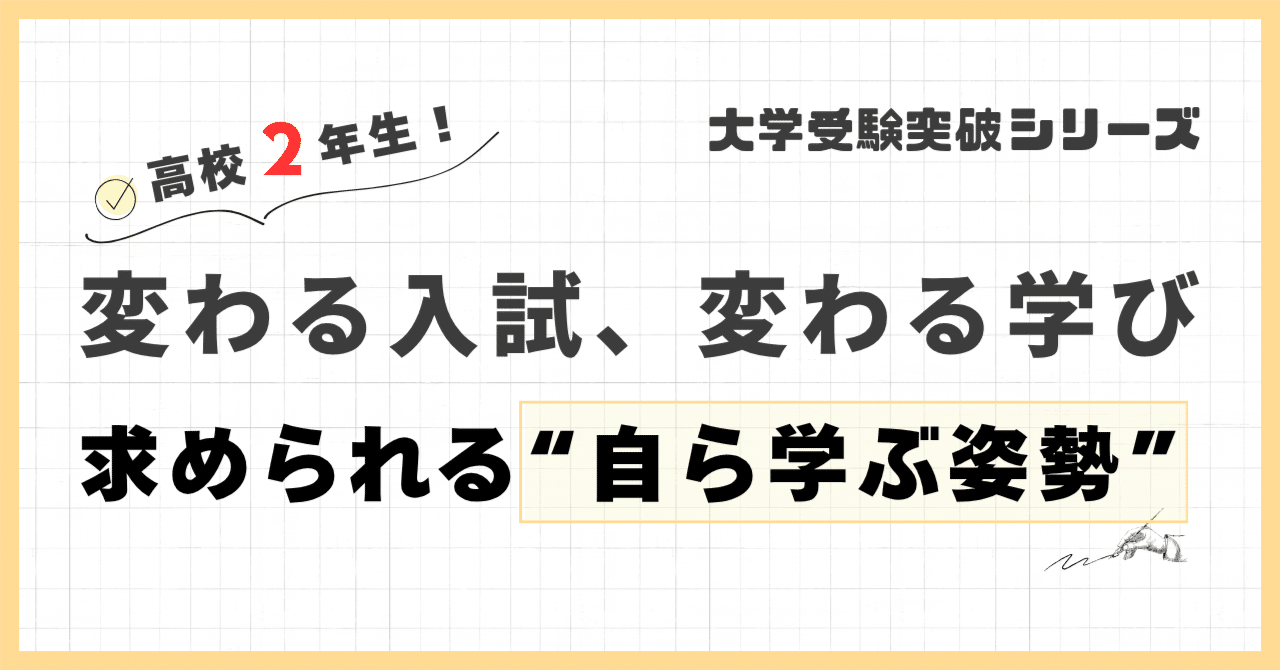ニュース&トピックス
教育情報・お知らせ
2025.11.15
【大学受験突破シリーズ】変わる入試、変わる学び!─求められる“自ら学ぶ姿勢”[高2生 対象]
2025年10月26日 10:00
大学入試は今、かつてない大きな変革期を迎えています。これまでのように「どれだけ知識を覚えたか」を競うだけでは、もはや通用しません。これからの入試が見極めようとしているのは、知識をどう使いこなし、どんな姿勢で学び続ける人なのかという「総合力」です。
では、この新しい時代の入試で“勝ち残る受験生”とは、どんな人物なのでしょうか。
1.求められるのは「知識の使い方」
文部科学省が掲げる「学力の3要素」――
-
知識・技能
-
思考力・判断力・表現力
-
主体性を持って他者と協働して学ぶ態度
この3つが、新大学入試の根幹です。特に、2021年度から始まった大学入学共通テストでは、「知っている」だけでなく「考え、説明する」力が問われます。複数の資料を読み取り、比較・判断して自分の意見をまとめる問題形式が増えています。つまり、知識を使って考える力が、合否を分ける時代になったのです。

また、2025年度からは新教科「情報」が共通テストに加わりました。すでに国立大学の約97%、公立大学の約44%が「情報」を必須としています。国公立志望者は、6教科8科目以上の対策が基本になるでしょう。
2.新傾向に強い生徒が持つ3つの力
近年の共通テストや大学個別試験では、契約書・説明文・広告文など、**「実用的な文章」**の読解問題が増えています。つまり、現実の社会課題に近い思考が求められているということです。
新傾向に対応できる受験生は、次の3つの力を伸ばしています。
-
情報を整理し、構造化する力
与えられた資料をそのまま読むのではなく、「何を伝えたいのか」「どのデータが鍵か」を整理し、関連づけて理解できる力。 -
他者の意見を踏まえて、自分の意見を言語化する力
特に小論文・面接・プレゼン型入試で問われる力です。感情論ではなく、根拠に基づいた論理的な説明ができる生徒が評価されます。 -
学びを自分ごととして語れる力
「なぜその大学で学びたいのか」「将来どう活かしたいのか」を、大学のアドミッション・ポリシー(入学者受け入れ方針)と関連づけて語れることが重要です。
これらの力は一朝一夕では身につきませんが、日常の学習で「なぜ?」を意識し、考えを文章や言葉にする習慣から着実に育っていきます。
3.多様化する選抜方式に備える戦略
現在、大学入試の約半数が総合型選抜(旧AO入試)や学校推薦型選抜で実施されています。一般選抜(学力試験型)のみで受験する時代ではなくなりました。
成功する受験生は、これら多様な入試方式の特徴を理解し、自分に合った戦略を早期に立てています。
たとえば、総合型選抜では「学びの探究レポート」「課外活動の記録」「志望理由書」など、提出書類の完成度が評価の分かれ目です。面接やプレゼンでは、表現力・コミュニケーション力が重視されます。
つまり、日常の学び方そのものが入試準備になるのです。
4.結果より「プロセスを成長に変える力」
受験期は、周囲が推薦や内部進学で早く進路を決めていく時期でもあります。焦りや不安を感じるのは当然ですが、ここで差がつくのは「メンタルを整える習慣」です。
ポモドーロ・テクニック(25分集中+5分休憩)など、時間管理の方法を取り入れて学習リズムを作ることで、自己効力感を保てます。
そして最も大切なのは、結果だけに一喜一憂せず、受験を“自分を成長させる過程”として捉える姿勢です。
「昨日の自分を超える」ことを目標にする受験生は、失敗を恐れず挑戦を続けられます。この姿勢こそが、大学・社会で求められる本当の“学力”です。
■ まとめ:新時代に生き残る受験生とは
新しい大学入試制度で成果を出す受験生とは――
確かな基礎学力を持ちながら、情報を自分の言葉で整理し、主体的に学び続ける力を持つ人です。
彼らは「与えられた課題をこなす人」ではなく、「課題を見つけ、学びながら解決する人」。
そしてその根底には、結果に左右されない学びへの前向きな姿勢があります。
時代が変わっても、「学びを楽しむ人」が最後に強い。
受験はゴールではなく、新しい知の旅のスタート地点なのです。

noteでEFG(旧久保田学園グループ)の教育情報を発信しています。
⇨https://note.com/kubotag