ニュース&トピックス
教育情報・お知らせ
2025.7.7
【大学受験突破シリーズ】 “解いたつもり”で終わる人が知らない過去問演習のホント [高3生対象]
大学受験における過去問演習の本質
━━「仕上げ」ではなく、「戦略の中心」です
大学受験を目指すうえで、過去問演習は避けて通れない重要なステップです。ただし、正しい理解と使い方をしなければ、その価値は十分に発揮されません。過去問は“仕上げの道具”ではなく、受験戦略の中心に据えるべき学習素材です。
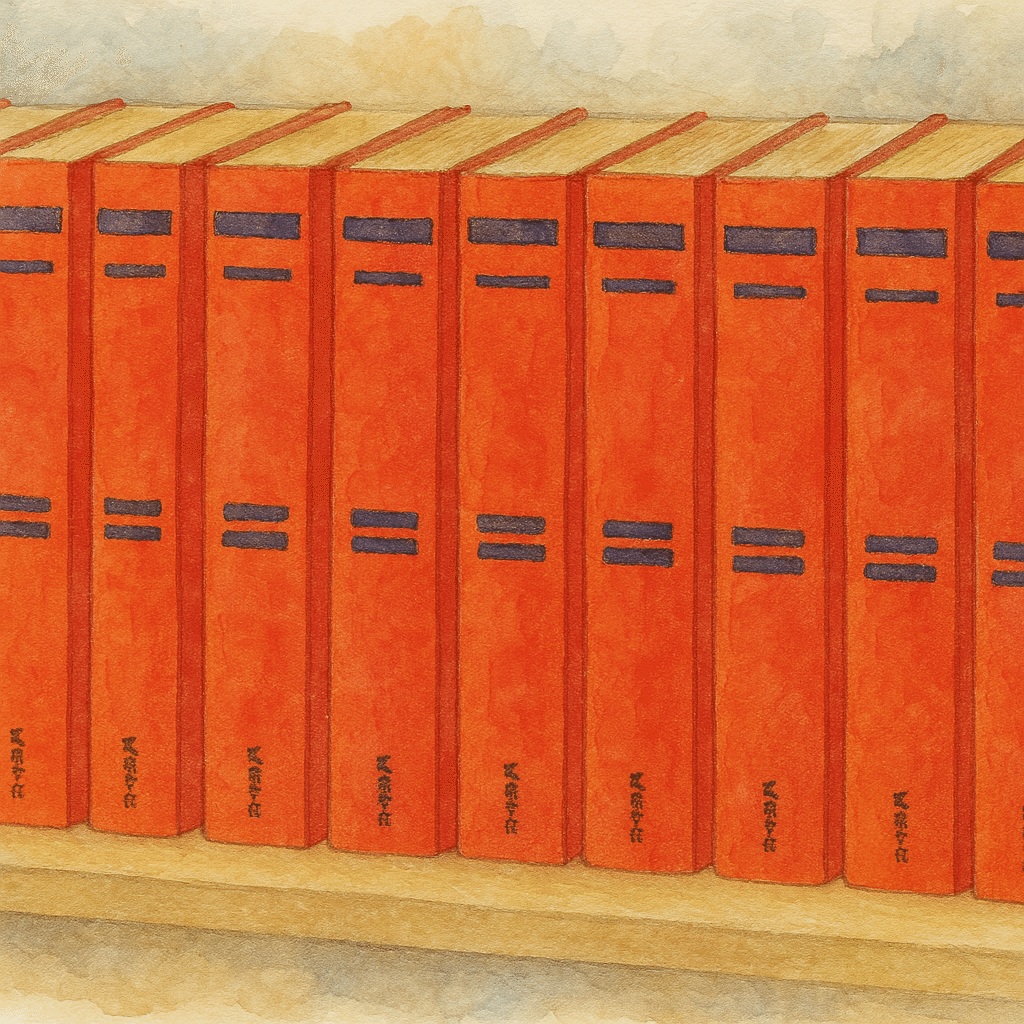
1|過去問の役割は「出題者の思考を知ること」
過去問を解くいちばんの目的は、志望校がどのような力を求めているのかを把握することにあります。「敵を知る」という表現は少し物騒かもしれませんが、まさにその通りです。問題の出され方、テーマの傾向、記述や選択肢の設計意図など、大学ごとの“問いのスタイル”を読み取ることが最初の一歩になります。
ただ解いて丸つけをするだけでは、学習効果は限定的です。大切なのは、「なぜ間違えたのか」「どう考えるべきだったのか」を深掘りすること。たとえ正解だったとしても、「たまたま」だったのか、「理解の上で」解けたのかを自分に問い直す視点が大切です。
2|「いつから、どのように」取り組むかが重要です
過去問演習は、受験直前になって慌てて取り組むものではありません。むしろ、学習全体の方針を決めるための“初期戦略”として活用することが効果的です。
たとえば、高校2年生の終わりごろに1年分だけ解いてみると、出題の雰囲気をつかむ良い機会になります。本格的に取り組むのは、高3の夏以降が目安。基礎がある程度固まったうえで、演習→分析→補強というサイクルに入るのが理想です。さらに直前期には、時間を計って実戦形式で演習し、本番の空気に身体を慣らしていくことも効果的です。
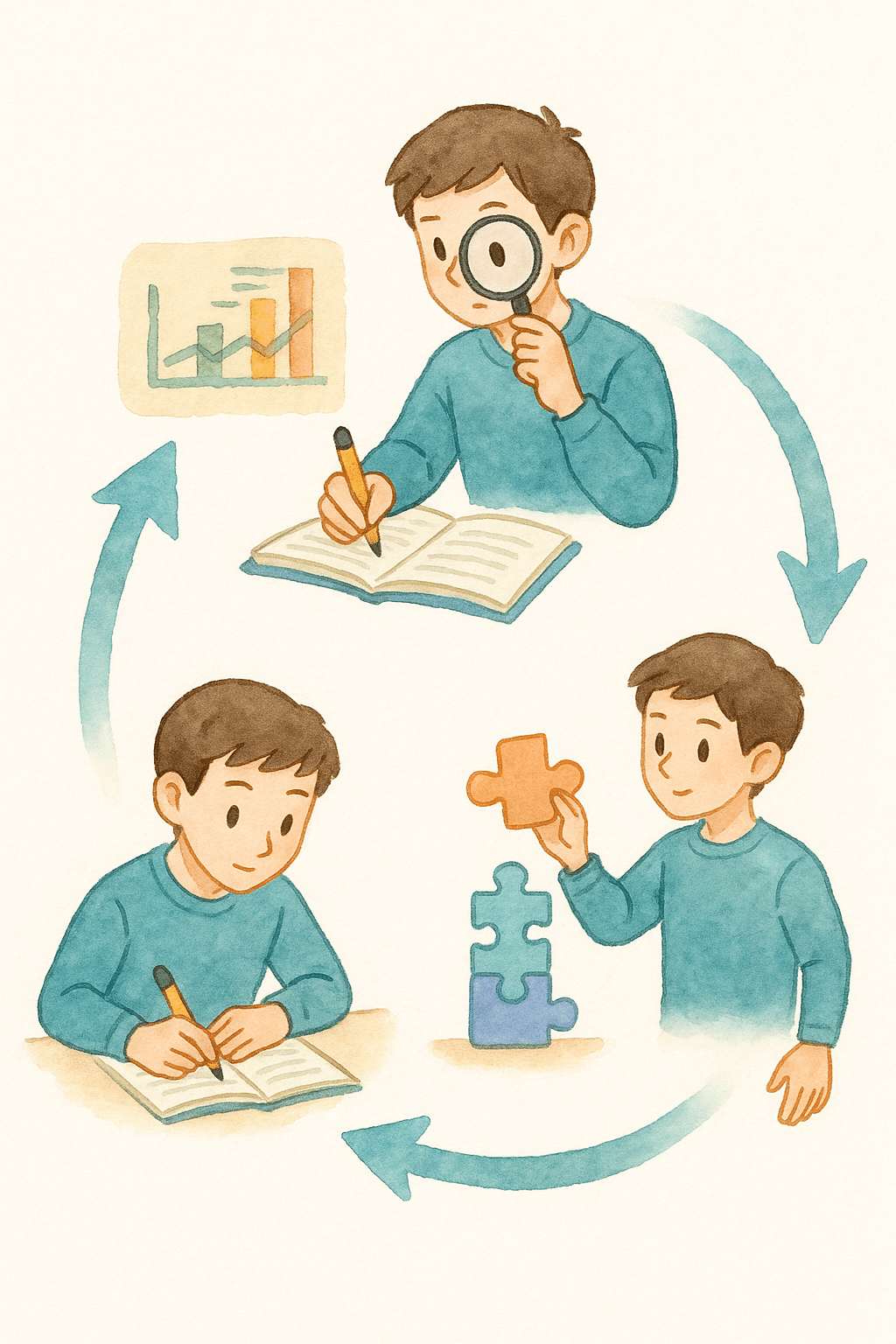
3|「復習」こそが、合格力をつくります
過去問の価値は、復習で決まるといっても過言ではありません。英語の長文なら、知らない単語や構文を抜き出し、音読や要約などで本文の内容を自分の中に定着させることがポイントです。解きっぱなしにせず、「もう一度読んだら解ける」状態にすることが、次の得点につながります。
記述問題では、自分の答案と模範解答を見比べ、論理の組み立て方や表現の工夫を学びます。可能であれば学校や塾の先生に添削してもらい、「採点者に伝わる答案」をつくる訓練を重ねていくことが効果的です。
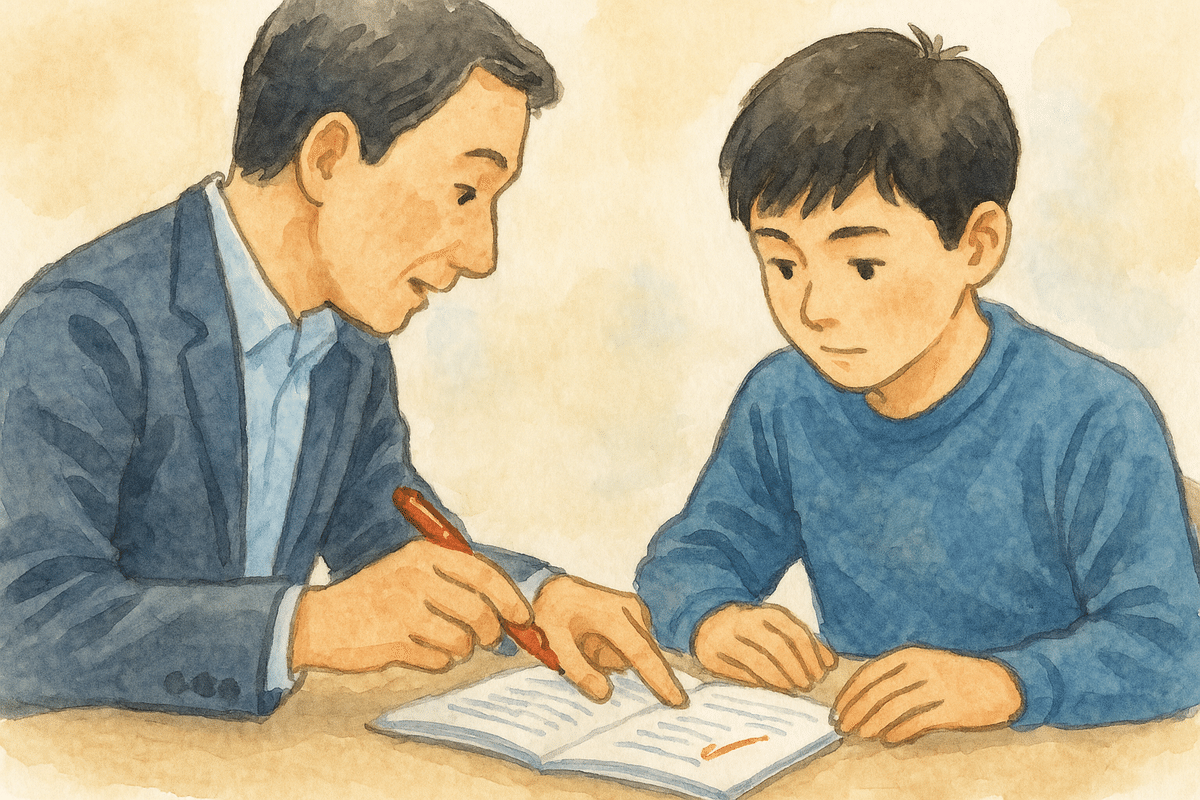
4|量と質、どちらも大事です
第一志望の大学については、少なくとも10年分、可能であれば20年分ほど取り組むのが理想です。出題パターンには必ず“意図”があります。たくさん解いていくうちに、その意図=「大学の思考パターン」が見えてきます。
さらに、時間配分の感覚を身につけることも不可欠です。本番では全問に完璧に取り組むのではなく、優先順位をつけて“取れる問題を確実に取る”戦略が求められます。そのためには、普段から時間を意識して過去問を解き、選択判断のトレーニングを積んでおく必要があります。
過去問演習とは、ただ問題を解く作業ではなく、自分の弱点を見つけ、補強し、合格の確率を高めるための分析と実戦の場です。正しく向き合えば、これほど頼もしい教材はありません。
目標とする大学に本気で近づきたいなら、過去問を“自分だけの武器”に変えていく覚悟をもって取り組みましょう。

noteでEFG(旧久保田学園グループ)の教育情報を発信しています。
⇨https://note.com/kubotag




